日差しが強くなってくる時期になると、梅干しを作るために、ざるの上に乗せられて天日干しされている梅をよく見かけますよね。
最近、自宅でも自家製の梅干しを作る方が増えているんです♪天日干しした梅を、赤紫蘇と一緒に塩漬けした梅干しは自分で作ったとなると、味わいもひとしおですね。
しかし、なぜ梅をそのまま漬けるのではなく、天日干ししてから漬けるのでしょうか?気になったことありませんか?今回は、梅干しを天日干ししてから漬ける理由とその効果についてご紹介します♪天日干しすることによって、より美味しく、そして食べやすくなりますので、これから梅干し作りにチャレンジしようかなと思われている方はぜひぜひ知っておいてくださいね!
スポンサードリンク
梅干しを天日干しすることには理由がある!その効果とは?
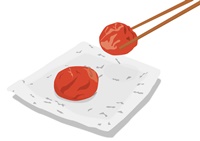 先ほどもご紹介しましたが、梅干しは天日干しにすることで、見た目だけでなく、香り(匂い)、食べやすさがぐんっっと増します♪そして長期保存できるようになるんです!
先ほどもご紹介しましたが、梅干しは天日干しにすることで、見た目だけでなく、香り(匂い)、食べやすさがぐんっっと増します♪そして長期保存できるようになるんです!以下に、天日干しする理由のポイントをまとめていますので、ご覧ください♪
○梅干しを天日干しする理由
「長期保存できるようになる」「美味しく食べられるようになる」の二つのポイントに分けてご紹介しますね!
≪長期保存が可能に≫
✅天日にあてることで、梅を殺菌して腐らないようにするため
✅余分な水分をとばすため
✅天日にあてることで、梅を殺菌して腐らないようにするため
✅余分な水分をとばすため
≪美味しく食べられるように≫
✅梅の風味を豊かにする効果がある
✅太陽の熱で梅の皮と実を柔らかくする効果がある
✅実をきれいな赤色にする効果がある
✅梅の風味を豊かにする効果がある
✅太陽の熱で梅の皮と実を柔らかくする効果がある
✅実をきれいな赤色にする効果がある
○日中だけでなく、夕方~夜ぎりぎりまで干す
ではどのぐらい干すのか?「天日干し」というぐらいですので、太陽が出ている時間だけ干すイメージがあるかもしれません。実は日中の太陽だけでなく、夜の夜露にもあてることによって、梅の皮や実がより柔らかくなっておいしい梅干しができるんです♪
日中の天日干しによって梅が乾燥したときに、果肉の中にできた塩の結晶が水分で溶けることで梅がしっとりなってくるんです。
一般的には8月の3日間昼夜晴れが続く日に天日干しを行います。この干す時期のことを「土用干し」と呼びます。なぜ、「土用干し」と呼ぶのか?わかりやすくまとめられているサイトがありましたので、一部抜粋してご紹介させていただきます。
「土用」というのは、日本に伝わる季節を表す言葉のひとつで、実は1年に4回あります。有名な「土用の丑の日」は、夏の土用のことです。他に、春、秋、冬のそれぞれの土用があります。日本には、立春、立夏、立秋、立冬という二十四節気があり、暦の上ではこの日から新しい季節がスタートします。土用というのはこの4つの日の前の日から数えた18日間のことを指します。つまり、夏の土用は8月8日頃にある立秋の18日前にあたる、7月20日頃に始まり、立秋の前日までとなります。地域によっては雨が多い日もありますので、様子を見ながら外に出したり室内に入れたりを調節することをおススメします!
出典:https://botanica-media.jp/287
天日干しの仕方を動画を参考にしたい方はこちらをぜひご覧ください♪3分ほどで分かりやすくまとめられていますので、ご紹介させていただきますね!
また、いざ天日干しをしようと思ったときに、「ざるがない」なんてこともあると思います。楽天で購入できる人気のざるをご紹介しておきますので参考にしてみてくださいね!
|
|
天日干しがうまくいかないとどうなるの?
○白カビが生えても大丈夫
梅が雨に当たってしまったり、日のあたりが不十分で天日干しが十分でないと、梅干しを漬けたときに梅酢に白カビが生える原因になってしまいます。この白カビは「産膜酵母」といわれるもので、基本的に無毒です。発酵食品の中でもカマンベールチーズのようにわざわざ発生させることがあるぐらいですので。
また、「白カビ」に見えて実は「塩」ということもあります。これら二つの見極め方は、お湯に溶かすことで見分けがつきます。
お湯に溶かして、溶けなければ「白カビ(産膜酵母)」、溶ければ「塩」になります。
このように梅干しに白カビが生えてしまっても問題はないのですが、気になる方はカビた梅だけをそっと取り除けば大丈夫です。表面だけに浮いた膜のような白カビも、そっとすくって取り除いて梅酢を足しておけば、そのまま漬けることができます。
スポンサードリンク
○外に天日干しできない場合は?
 外に梅を十分に天日干しできない場合は、梅を干さずにそのまま生まずに漬ける「梅漬け」という漬け方もありますので、こちらをおすすめします。
外に梅を十分に天日干しできない場合は、梅を干さずにそのまま生まずに漬ける「梅漬け」という漬け方もありますので、こちらをおすすめします。
車の交通量が多い地域で外に干すのが不安な場合や、アパートやマンションなど干す場所がない場合も、梅漬けにするといいでしょう。
梅漬けにする場合は、天日干しをしない分賞味期限は短いため、3か月~半年で食べきるようにしてくださいね。
ちなみに、ジップロックと瓶だけで作れる方法の動画がありましたので、ご紹介させていただきますね♪
どんな風に天日干ししたらいいの?コツとみんなの天日干しをご紹介♪
○おいしい梅干しができる!天日干しのコツ♪
ちょっとしたコツで天日干しは上手に行うことができます。以下参考にしてみてくださいね!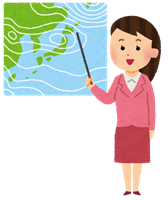
・昼夜、天気のいい3日間に行う
・ざるやネットなどを使い、風通しを良くする
・梅の様子を見て、ひっくり返す
・カビの原因になるため、雨に当たらないようにする
・ざるやネットなどを使い、風通しを良くする
・梅の様子を見て、ひっくり返す
・カビの原因になるため、雨に当たらないようにする
○手作り梅干しがブーム!?みんなの天日干し
Array朝から梅干しの土用干しして、やっと終わった。
— ちびノリダー (@Ranchan2929) July 24, 2016
午前と午後で2時間くらいかかった。
梅酢も3リットル。 pic.twitter.com/nD6bTdJyrM
Array今日は曇りの天気予報だったけどはずれ、朝から快晴で嬉しい。干し足りない梅を干してます土用干し4日目。 pic.twitter.com/quwCjNQ1xj
— azukKi (@azukki_) July 22, 2016
Arrayわが家の梅干し作りの経過ですが、赤紫蘇が出たので、葉を摘み取ってボールに入れ、塩をまぶしてなじませ、赤黒い汁が出るまでもみ、この汁をきつく絞って梅の上にのせました。このまま土用干しまで置いておきます。 pic.twitter.com/3pkd6SHNHN
— 林恵子(はやしけいこ) (@keikokumo) July 8, 2016
Array長い雨でなかなかできなかった白梅干しの天日干しを実現でき。それにしても今年の梅はそばかす美人さんの多いこと。これも里山の自然のなせる業か。#白梅干しの天日干し pic.twitter.com/xsDMiZRPc1
— 上原まるこ (@marcosanpo) July 29, 2019
スポンサードリンク
まとめ
いかがでしたか?今回、梅干しを作る際に行う天日干しをする理由についてご紹介しました。一見、難しそうな梅干しづくりですが、コツをつかめば楽しみながら作れるんです!さっそく試してみたくなりますよね♪
筆者の祖母も、毎年大量の梅を仕入れ、自家栽培した赤紫蘇と一緒に天日干しして梅干しを作っているのですが、昔から夏の暑い時期の風物詩になっています。その家庭によって干し方や塩加減に違いがあるため、その家庭の味が出た梅干しになりますよね。
申年に漬けた梅は縁起物と言います。天日干しのコツをつかんで、今年はおいしい梅干しを手作りしてみてくださいね♪
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19659499.cbb4c2cd.1965949a.0b23b831/?me_id=1282688&item_id=10002259&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-designshop%2Fcabinet%2F217300000054.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-designshop%2Fcabinet%2F217300000054.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
